

AIやボットの存在を近未来を題材にした映画や、つい最近のテクノロジーだと思っているかたも多いかと思います。
ただ実際には、AIやボットはもっと前から存在していました。その概念自体はギリシャ神話の中にすでに見られると主張する人もいるほどです。今回の記事では、実際に機械と人間の本格的な交流が始まった1950年代から今日に至るまでの歴史を簡単にたどってみたいと思います。
ボットがボットたる所以、そして好むとも好まざるとも、私たちの日常にボットが欠かせない存在になるまでに、どのような過程があったのかを見ていきましょう。
ボットとは?
ボットとは自動化技術の一種で、特定のタスクを人間の介入なしに遂行することができるものです。タスク開始のきっかけになるのは人間ですが、その後の作業はボットが自動的に行ってくれます。
つまり、ボットは人工知能(AI)の一形式ということになります。私の同僚のMimi AnはAIのことを、「話す、見る、学ぶ、交流する、社交する、推論するなど、人間ならではのことができる技術」と形容していますが、まさにぴったりの定義だと思います。
SiriやGoogleアシスタントなど、今日の私たちになじみのあるボットの多くは、まるで人間のような受け答えをすることができ、十分にAI的であると言えます。例として人間とGooleアシスタントとのやり取りを見てみましょう。
現代では、大部分の人がボットを日常的に利用しています。毎週あるいは毎日音声アシスタントを利用しているという人の割合は55%にも上ります。カスタマーサービスやプロモーションなど、さまざまな分野のさまざまなニーズに、ボットが使用されており、時にはボットだと気付かずに利用している場合もあるでしょう。では、ボットは実際にどのようなことができるのでしょうか。ことの始まりから見ていきましょう。
ボットの歴史
1950年代
チューリングテスト
チューリングテストとは、イギリスの数学者兼コンピューター科学者のアラン・チューリング氏により考案されたテストで、模倣ゲームとも呼ばれています。最も基本的なチューリングテストでは、A、B、C、3名の役割を設定します。
- Aは機械で、Bは人間です。
- Cは質問者で、質問をコンピューターに打ち込みます。
- CはAとB両方から回答を受け取ります。
- Cは回答を見て、AとBのどちらが人間かを判断します。
ただ、当時はデータベースの情報量が限られていたため、コンピューターは限られた回答しか返すことができませんでした。そのため、テストが進むに従いコンピューターの回答内容が尽きてしまい、どちらが人間か明白となってテスト終了となるのが常でした。
物議を醸した2014年のチューリングテスト
2014年、英国レディング大学で「チューリングテスト 2014」が開催されました。このテストでは、30名の審査員がCの役割を務めました。テストでは、コンピューターの全回答のうち、審査員全員が「人間の回答だ」と信じた回答の割合が30%を超えたら、そのコンピューターは「合格」したと判断されます。
そして2014年、ついにチューリングテストに合格するコンピューターが登場します。このコンピューターは、13歳のウクライナの少年「Eugene Goostman(ユージーン・グーツマン)」という設定で、全審査員が33%の確率で人間だという判定を下しました。.
世界で初めて、コンピューターがチューリングテストに合格したわけですが、この結果には賞賛と批判の両方が巻き起こりました。米国公共放送局(NPR)の人気番組「All Things Considered(万事を考慮してみると)」でも議論になったほどです。Eugene Goostmanの能力に懐疑的で、初歩的なAI技術に比べて本当に優れているのか疑問視する人も数多くいました。
とはいえ、チューリング氏はこの分野の第一人者と見なされており、今日のAIへの礎を築いたと考えられています。その5年後の1956年、ダートマス大学に在籍していたジョン・マッカーシー氏が「Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence(人工知能に関するダートマス夏季調査プロジェクト)」を開催します。
このプロジェクトは、「Dartmouth Workshop(ダートマス会議)」とも呼ばれており、後に同大学におけるAI研究部門へと発展していきます。また「Artificial Intelligence(人工知能)」という言葉は、このプロジェクトで始めて使用されたと言われています。
1958年、マサチューセッツ工科大学に移籍したマッカーシー氏は、LISPというプログラミング言語を開発します。この言語はすぐにAI分野で好んで使用されるようになり、現代でもこの言語を好む人は少なくありません。
コンピューター科学者として有名なアラン・ケイ氏を含む多くのAI研究者が、「これまで開発されたプログラミング言語の中で最も優れた言語」と絶賛しています。
1960年代
ELIZA
1960年代のAI分野における最も大きな成果は、1966年にマサチューセッツ工科大学のジョセフ・ワイゼンバウム氏が開発した「ELIZA(イライザ)」でしょう。ELIZAという名前は、音声学の教授であるヒギンズがコックニー訛りを話す花売り娘のイライザに洗練された話し方を訓練するという戯曲ピグマリオンにちなんでつけられました。
ELIZAはスクリプトに基づいて人間と対話するボットで、精神療法士をシミュレーションしたDOCTORというスクリプトが広く知られています。しかし、いかんせん当時の技術は限られており、ELIZAの語彙にも限界がありました。
私も実際にELIZAと対話してみましたが、まったくかみ合わない会話になりました。(実際にELIZAを試してみたい方は、カリフォルニア大学フラトン校心理学部のご厚意によりこちらで試してみることが可能です。)
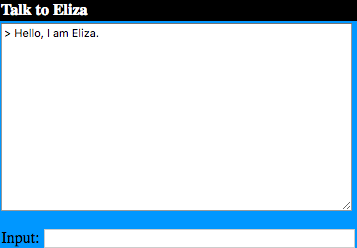
ただ、ワイゼンバウム氏は自らの論文のなかでELIZAのことを「英語の知識は限られているが、非常に良い耳を持っている」人になぞらえ、大いに成長の余地があることを主張しています。
VentureBeatのNicolas Bayerque氏も、「こうした初期の発明から分かったことは、人間には、人間同士のコミュニケーションと同じように、機械とコミュニケーションしたいという強い思いがあるということだ。ただ当時は、それを実現するための技術的な知識が足りなかったにすぎない」と語っています。
しかし、1966年に発表された『ALPAC報告書』がAI研究への逆風となりました。このレポートは、ALPAC(自動言語処理諮問委員会)という委員会がまとめたものですが、全体的に機械学習に懐疑的で、AI研究に対する政府の資金援助打ち切りのきっかけとなりました。
今でも多くの研究者が、この報告書のせいでAI研究に何年もの遅れが出たと考えています。こうした背景により、1970年代に入るまで、ボットの分野ではあまり大きな進展は見られませんでした。ただ60年代後半にも、スタンフォード研究所が開発した「Shakey」のように、「言語機能の限られた」自律ロボットの開発は行われていました。
また、 1969年には、最初の「国際人工知能会議(IJCAI)」が開催されました。この会議はその後も隔年で開催され、2016年からは毎年開催されています。だたAIがふたたび大きな注目を浴びるようになるまでには、もう少し時間がかかります。
1970年~80年代
Freddy
1970年代初頭、エディンバラ大学の研究者たちにより非言語ロボット「Freddy」が開発されました。Freddyは人間とコミュニケーションすることこそできなかったものの、人間の介入なしに、簡単な部品の組み立てを行うことができました。
Freddyの最も画期的な機能は、カメラから入ってくる視覚的な情報を基づいてタスクを実行できたことでした。つまり、Freddyは部品を「見て」組み立てることができたのです。しかし、その速度は非常に遅く、タスクを完了するのに16時間もかかりました。
医療分野におけるボット
1970年代は、医療分野にボットが活用され始めた時代でもありました。1972年、スタンフォード大学医学部に、「MYCIN」というシステムが導入されます(このシステムはエキスパートシステムとも呼ばれていました)。
同システムは、医師が診断をする際に尋ねるのと同じような質問を患者に尋ね、専門家たちがまとめたナレッジベースを参照して、回答を導きだすというもので、患者の感染症を特定するのに使用されました。
さらに1970年代半ばには、同様の医療用ボット「INTERNIST-1」がピッツバーグ大学で開発されました(ちなみに、このボットは、マッカーシー氏のLISPを使って開発されています)。
これは、後に「Quick Medical Reference(医療診断クイックリファレンス)」という、複数の診断を下すことのできる意思決定支援システムへと発展しました。ただ、このシステムは現在は使用されていません。
AIに関する大規模な会議
1980年代初頭になると、「Conference of the American Association of Artificial Intelligence(アメリカ人口知能学会)」を始め、AIに関する大規模な会議が開催されるようになります。
また、「AARON」と呼ばれる、独自の抽象作品と具象作品を制作できるボットも誕生しました。このボットの作品は英国テート・ギャラリー、アムステルダム市立美術館、サンフランシスコ近代美術館などで展示されました。
最近は、自律走行車が話題になっていますが、自律運転に使われている技術は、実は1980年代にまで遡ります。1989年、カーネギーメロン大学のDean Pomerleau教授が「ALVINN」という車両を開発しました。
ALVINNはAutonomous Land Vehicle In a Neural Network(ニューラルネットワークによる自律陸上車両)の略で、米軍の資金援助により開発された車両でした。ALVINNは人間の運転を学習した後、カメラからの映像をコンピューターで解析することにより自律運転することができました。
1990~2000年代初頭
消費者向けボットの誕生
1990年代以降、ボットの開発目的は消費者向けへと大きく転換していきます。このころ流行した初期のテレビゲーム、特にプレーヤーが操作コマンドを入力する形式のゲームは、消費者向けボットの原型と考えることができるでしょう。
もうひとつ、この年代で触れておかねばならないのが、1996年に発売された「たまごっち」です。この製品は当時「ボット」とカテゴライズされていたわけではありませんが、たまごっちの双方向性は、まさにボットそのものです。
手のひらサイズのコンピューター「ペット」であるたまごっちは、本物のペットと同じように、電子的に餌をやり、遊び、トイレの世話をする必要がありました。
さらに1990年代は、ロボットがよりスマートになり、その能力が向上した時代でもありました。1997年の公式ロボカップゲームのように、自律してサッカーができるロボットなども誕生しています。ロボカップでは、ロボットだけで構成された40チームが、テーブル上に設定されたフィールドで試合を戦いました。
SmarterChildの登場
2000年になると、人間の自然言語を解するボット「SmarterChild」が誕生します。MotherboardのAshwin Rodrigues氏は「何百万人というアメリカ人のインスタントメッセンジャーの連絡先一覧に住んでいたロボット」と説明しています。
SmarterChildは、質問に対する回答のバックログがプログラミングされたボットで、ユーザーと自然言語でやりとりすることができました。Siriなどの音声検索ツールの原型と言えるでしょう。
SmarterChildを開発したActiveBuddy社の共同設立者兼CEOのPeter Levitan氏は、Motherboardのインタビューでこう語っています。「Googleもすでに登場していたし、Yahoo!も強力だった。それでも、知りたい情報にたどり着くには何分もかかっていたんだ」 そこで同社は会話形式で情報を瞬時に得られるボットの開発を思いつきます。
「たとえば、『昨日のヤンキースの試合結果は?』とたずねれば、瞬時に結果を表示してくれる」ようなボットです。同氏の言葉を借りれば、SmarterChildは当時「人々に衝撃を与えた」技術でした。

すぐにこの技術に目を付けたMicrosoft社がActiveBuddy社を買収しましたが、その後このサービスは停止されています。
2000年代初頭は、自律走行車にも進展が見られました。スタンフォード大学で開発された自律走行車「Stanley」は、モバーヴェ砂漠で開催されたロボットカーレース「DARPAグランド・チャレンジ」を10時間未満で完走するという快挙を成し遂げました。
Bayerque氏は、2000年代をボット進化の時代として見ています。その背景にあるのはスマートフォンの爆発的な普及です。当初、開発者たちはデスクトップ用のウェブサイトをスマートフォンの小さな画面に収めるのに苦労していました。
この課題に対処するために、ユーザービリティやレスポンシブネスといったことが考えられるようになりました。同氏いわく、「より優れたインターフェースはあるか?」という問いを追求していった結果行きついたのが、人間相手のように話せるインターフェースだったのです。
2011年以降
Bayerque氏は、AI技術の進化の理由としてスマートフォンの普及を挙げましたが、同じように、音声認識機能を備えたAIパーソナルアシスタントの登場により、消費者がボットを利用する機会が急増しました。
ただ実は、これより前にいくつか家庭用AIが登場していました。その開発企業のひとつがiRobotです。同社はもともと軍需企業でしたが、後に自動掃除機「ルンバ」のメーカーへと転身しています。ワシントンポスト紙はルンバを「家庭用ロボット」と呼ばんでいます
ただ、ルンバは人間の音声を認識して会話することはできませんでした。部屋の掃除はしてくれますが、それ以外の機能はありません。ですから、2011年に発表されたSiriは非常に画期的でした。
スマートフォン上で、私たちの質問に音声会話で瞬時に答えてくれます。検索エンジンを開く必要もありません。この技術には将来性があり、さらに改良の余地もあったので、他の企業も続々と音声アシスタント市場に参入しました。
現在では、以下の4社が音声検索における主要企業となっています。

まもなく、各メーカーは音声検索と、IoT(モノのインターネット)を組合わせていきます。IoTとは、家電製品や照明、セキュリティシステムなどをインターネットに接続し、遠隔で制御する仕組みです。
Siri登場の3年後には、すでにAmazonが「Echo」をリリースしています。Echoでは、Alexaと名づけられたボットが、天気や単位の変換に関する質問に答えてくれたり、住宅におけるさまざまな自動化を制御してくれます。
もちろんGoogleも黙っているはずがなく、2015年にGoogle Homeをリリースしています(EchoとGoogle Homeの違いに興味がある方はこちらの記事(英語)をどうぞ)。
さらに、音声検索や音声アシスタントなど個人レベルでの利用だけでなく、サービス部門へボットを利用する企業も増えてきました。たとえば、Facebookは、Messengerアプリにボットを統合できる機能を提供しています。
これを使えば、ユーザーが配信登録しているコンテンツ(天気、交通情報など)、レシピや配送通知などカスタムメッセージ、リアルタイムの自動返信などをチャット形式でユーザーに自動配信することができます。以下は、有名企業のLouis VuittonとEverlaneがMessengerボットをカスタマーサービスに活用している例です。
.png?width=510&name=Screen-Shot-2016-04-13-at-12.27.47-PM%20(1).png)
さらに、MYCINやINTERNIST-1が開拓した分野でも、「Healthtap」などのサービスが誕生しています。同サイトは、症状に関する患者の質問に、医師の意見がまとめられたデータベースから答えを見つけて自動的に回答してくれるサイトです。
ただ、この記事で紹介したツールやサービスは、氷山の一角にすぎません。HubSpot(ハブスポット)のAnがまとめたこちらの調査結果(英語)を見ていただければ分かりますが、ボットは多岐にわたる目的で使用されており、その一覧を作成することは事実上不可能です。
さらにその先へ
2017年9月、パーソナル アシスタント ボットの「Olly」がクラウドファンディグサイトのIndiegogoで発表されました。Engadgeによると、基本的な機能の大部分はEchoやGoogle Homeと変わらないものの、Ollyには素晴らしい「個性」があるそうです。
しかもその個性は使う人によって変わります。実は、Ollyは使用者の習慣や日常の行動を学習し、それに合わせた対応ができるのです。また、音声による指示を待つだけでなく、カメラとマイクから入力される使用者の表情や声の調子から感情や気分を読み取り、自ら何か提案したりすることもできます。
以前はSFのなかにしか存在しなかったボットが、今や現実になりつつあります。こうしたボットに対する反応は、人それぞれですが、少なくとも「つまらない」と言う人はいないでしょう。これからも、ボットの進化には目が離せません。また進展があれば記事でご紹介していきます。




